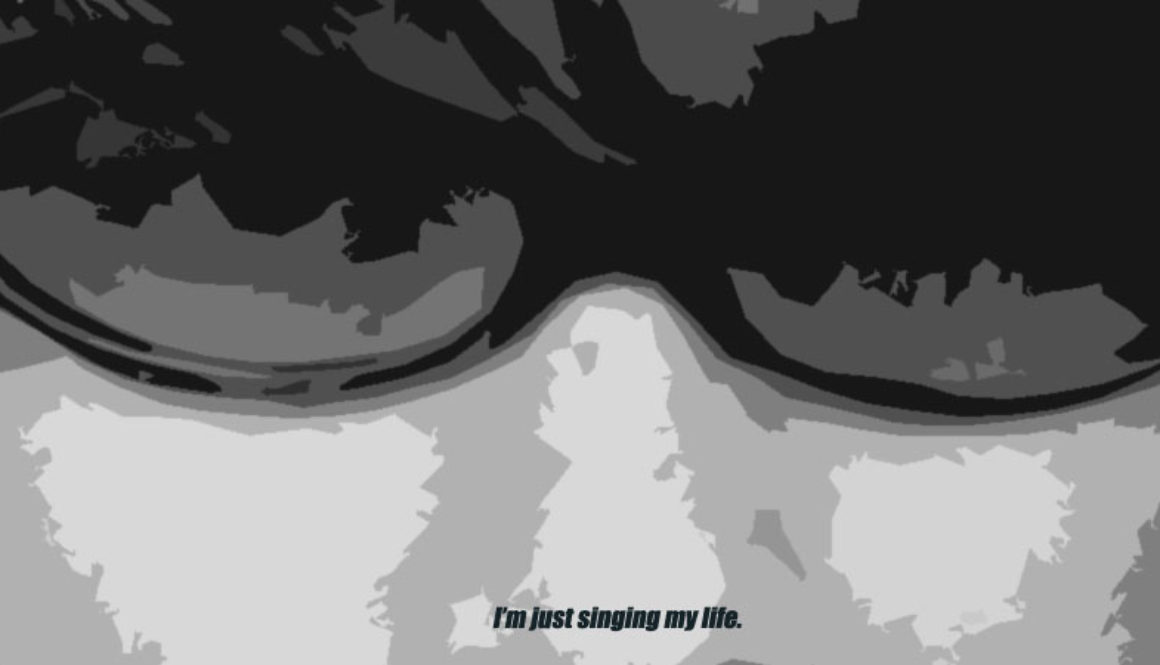近頃の話
最近アイデアが浮かばない。
眠ったまま起きなくなったどこかのお姫様のよう(んなわけない)に、イメージすらもぼやあんとして口をつくこともない状態。
かと言って、全く夢を見ないわけではなく、むしろ最近は夢をよく見る。
続きもののドラマのように毎晩前日の続きを体験する。
ただ、全て等身大の自分ではなく、時には車屋で宣伝に苦労してもがいている営業マンにだったり、時には最高のおもてなしで人生の記録を刻むカメラマンだったり、そして時には、その日暮のしがない浪人だったり(最後だけ時代が違う)と、バラエティに富んだストーリーの中を旅しているのだ。
その中の1つに、歌を歌う自分がいて、渾身の曲だと得意げに大声で歌うも誰も立ち止まらない日もあれば、暇つぶしに作った歌を脱力感たっぷりで歌えばドームで大喝采を受けてなんとも複雑な心持ちの日もある。
では、その曲たちはというと、ミスチルの某歌よろしく、朝起きると全く覚えていない。
何でもいい、どっちでもいいからメロディを思い出せればいいのであるが、起きた瞬間に微かな映像と共にぱっと消えて失せる。
何か方法はないだろうか。
もしかしたら、寝言を録音してみれば、何か糸口は見つかるだろうか、と思う今日この頃である。